�R�����S�̓��c�_�ƃT�C�m�J�~�M�@by�@�Ƃ��܂˂� 2024/07/20
1.�����̍\������̍l�@
���āA�R���ɈڏZ����������C�ɂ͂Ȃ��Ă����B
�����Ƃ��ڂ�����{�̐Β�������A�Αg�݂���d��ɉԛ���̎��R�������Ă���B
�_�Ђ��H�K���H���ׂ�ƁA����͊ېΓ��c�_�Ƃ��A���ɍb�B�ɂ͑����������B
�x�Ɠ`���̏o�_���̘b�ɓo�ꂷ��_�Ђ̒����Ɠ����\�����ƒm�����̂����N�O�̂��ƁB
�܂��R�����ɂ́e�v�ߓy�f�Ƃ����n��������A���݂�JR���C�g�������v�ߓy�w���瓌����тɂ�����ŁA�N�i�g�_�Əo�_���ɊW���Ă��鎖�͋^���悤���Ȃ��B

 �B��s��������̏�A�T�C�m�J�~�A�E�͎\�_�B�H�t����͏������ꂽ�Ƃ�����J���Ă���B�܂��H�t����͓��Ă����Ƃ������B
�B��s��������̏�A�T�C�m�J�~�A�E�͎\�_�B�H�t����͏������ꂽ�Ƃ�����J���Ă���B�܂��H�t����͓��Ă����Ƃ������B
��{�̒��͒��A�i�V���C�V�j�A���A���A���A�|�������A�����͏o�_�l�������Ƃ��Ă��悤���B�����ڂ́A����l���ڂɂ���A�ɐ��_�{�̐_�������⎭�������Ƃ͂��Ȃ�قȂ�B
����Ă������J���Ă���_�́A���X�喾�_�Ƃ��A�`���̈�א_�ЁA�L�I�̃A�}�e���X�̌n�̐_�X�Ƃ͈قȂ�N���������Ƃ͖��炩���B�v�͏o�_���̃T�C�m�J�~�M�Ɍ�������ƍl����B������Ώ�Â��͍b�B�ɂ͏o�_�����Z�ݒ����Ă����Ƃ���ƁA�u�b�㍑�ΐ��`���E�R���`���@�Ñ�Č��v�ŏq�ׂ��A��_�_�Ђ�ۍ��F���q�̏R��̘b��A�v�ߓy�̒n�����X���[�X�ȗ���Ƃ��ė����ł���B
�܂����Ղ�Ƃ��ẮA�㐢�̂��ƂƂ͂Ȃ邪�b�{���c�_��Ƃ����A�]�ˎ��ォ��b�{�鉺���ōs��ꂽ�������̓��c�_�炪����A���݂����������̋ߏ��ł͒��A����W���ɒ��菄�炵�āA����s���Ă���B

 ��A���v�X�s����(52��������)�A������T���^�F�H�A�T�C�m�J�~�A�H�t�_��
��A���v�X�s����(52��������)�A������T���^�F�H�A�T�C�m�J�~�A�H�t�_��

 ��A���v�X�s����V�������_(52����)�̓��c�_�A�������̍Ղ�̎��ɂ͒��S�I�ȓ��c�_�B���̐͏H�t�_�Ђƍ��܂�Ă���B
��A���v�X�s����V�������_(52����)�̓��c�_�A�������̍Ղ�̎��ɂ͒��S�I�ȓ��c�_�B���̐͏H�t�_�Ђƍ��܂�Ă���B
2.�����̋N���̍l�@
���̒����̍\�����قȂ�̂��H
�����̋N���Ɋւ��ẮA�Ⴂ���ɒ��ׂ��Ƃ��ɂ́A���N�����ɂ́A�`���g�x�L�Ƃ��������~�܂��������\���������邱�Ƃ͒m�������A
Wiki�́m�����n�o�T:�t���[�S�Ȏ��T�w�E�B�L�y�f�B�A�iWikipedia�j�x������p����
�u�����l�ފw�I�Ȋϓ_
���݂̉_��Ȃƃr���}�Ƃ̍����n�тɏZ�ރA�J���i�p��FAkha�A�����ł̓n�j���j�́u�p�g�H�[�E�s�[�i����̖�j�v�Ƃ������̓����̖�ł́A��ɖؒ���炵�������u����邱�Ƃ�[17][18][19]�A����͂������`�������镗�K�����邱�Ƃ����n������������[10]�������Ă��邱�Ƃ���A���{�̐_�Ђł悭������u�����v�̌��^�́A�A�J���炪���]���悩��쉺�A���Ă���O�A���]����ɏZ��ł�������i�S�z�l�ł���������j�́u�����v�ł͂Ȃ��̂��A�Ƃ�����������B�A�J���̑��̖�ɂ͒��̖،`���u����邪�A���l�̒��̖،`�͓��{�ł̈�앶���̎n�܂�Ƃ����퐶����̈�ւł���r��E�]����Ղ�㕌���Ղł��������Ă���[12]�A�܂����ɂ������̈�ւł����l�ł���[20]�B�v
�n�j���Ɠ��{�l�Ƃ̕����l�ފw�I�ȋ��ʓ_�͑����A�����̓~���I�������l�ŁA�퐶�l�̃��[�c�����]����ɂ���A���уW���|�j�J�Ă̐��c���ƂƂ��Ɏ������܂ꂽ�Ɛ����ł���B����l�̂x��`�q�n�v���^�C�v�ł́AO1b2�n�̐l���퐶�l�̖���Ƃ���A���ݖ�2�`3�����x�̓��{�l������ɂ�����B
�����ł́A�ؓ�̐l��3����O1b1�ŁA���]�����̐��ނœ쉺�����W�c�Ƃ������Ă��邪�A�~���I���̓`���ɂ́A�c��͂��Ƃ��ƒ��]������Ő������Ă������A�N���҂ɂ��y�n��D��ꂿ�����ɎR�ԕ��ɓ����Ă������Ƃ���A������ړ��̑傫�ȗ���ŁA���݂̒������������ƂȂ����悤���B
���]��������́A���c��삳��鉷�уW���|�j�J��̔��˒n�Ƃ���������Ă���A���̌�͌���ɂĒ��]������������A�����͒S�����ƍl����B
�����āA���ތ�ɐ��Ɉړ������{�ɓ��B�����̂��A����O1b�n��O1b2�̖퐶�l�Ƃ������ƂɂȂ�B
�����́AKorean Gene and uniqueness�u���{�l�̋N���Ƃ��Ă̒����̏�������.�v
http://www.hpcreating.com/Japanese.html
�ł́A�uThe ChinaMAP analytics of deep whole genome sequences in 10,588
individuals�v��SNPs�}�b�s���O�́A���݂̃~���I������`�I�ɓ��{�l�ɋ߂��Ƃ������͌��ʂ���A�ߋ��Ƀ~���I���̂Ƃ���c��W�c���n�������\����_���Ă���B
�@�����Ƃ��ẮA�퐶�l�����݂̒������������̑c��̓���̈�W�c�Ȃ݂̂ł͂Ȃ��A�����W�c�̒f���I�ȕ�����̓n���ł������ƍl����̂����R�ȋC������B
�n�������̖��(���A�z�̖ł����݂̂ł͍���Ȃ�����)�A�n���̃��[�g(�傫�Ȗ��ł͂Ȃ����A�P��ł͂Ȃ����낤)�A�n�q���@�Ȃǂ��܂߂āA���㌟�����̂��낤�B
3.�n�j���Ɩ퐶�l�̋��ʓ_
���ɁA�n�j���Ƃ̋��ʓ_���m�F����A�X�ɗ������[�܂�Ǝv���B
Wiki�́m�n�j���n�o�T:�t���[�S�Ȏ��T�w�E�B�L�y�f�B�A�iWikipedia�j�x������p����
�u���{�n����
�퐶����̈�Փ����猩�������l����DNA�E���i������v���͍������Ă���A�哤���g�����[���□�X����ɉ̊_�̕����A���R���q�̃A�j�~�Y�������{�Ƃ̋��ʓ_�������B
�n�j����4���I�ȍ~�ɐ���瓦��ē쉺�����Ƃ���邪�A�y�����̓��{�܂œ��B���Ă������Ղ��������Ă���B
����
�n�j���̓x�g�i����I�X�E�~�����}�[�E�^�C�ɂ��ڏZ���Ă���A���n�ł̓A�J���ƌĂ�Ă���B���Ƀ��I�X�ɏZ�ރA�J���̑��̓�����ɂ͖ō�����傪����`�����{�̍ŌÂ̒����Ɏ��Ă���B���{�̂悤�ɖ���������g�ݍ��킹�Ă͂��Ȃ����A�����̌`��Ɩ������̖������Ă���_�ň�v���Ă���A��̏�ɒ��̒������������Ă���ꍇ������B���{�̖퐶����̈ꕔ��\���玗���`�̒���͂������������������������B
�܂������̕��K�͎l��ȗ��R�ɐ��ރC���i�R���j�Ƃ����ʂ��Ă���`�x�b�g���痬��钷�]�i�g�q�]�j�t�߂ɑ��݂������]�����S����̎q���Ƃ����C���ƌ��X�̐����悪�߂�������߉��ł���ƍl������B�v
���Ȃ艓�����������A�ؓ삩��n�����Ă����퐶�l�ɐ_�Ђ̒����̋N�������邱�Ƃ͐����͂�����B���̍ہA����z�̕������z�����Ă����̂��낤�A�ܘ_�퐶�l�̕ʂ̏W�c�ɂ́A�����̉z�l����l���������Ƃ����邩������Ȃ��B
���A�|�������Ɋւ��ẮA�����Ƃ������t���g���͕̂s�K�ȋC������B
�@�\�I�ɂ́A�_�̗̈�Ƒ��E�Ƃ̋��E���������́A�_�Ђ̓�������������̂œ����ł͂��邪�A��͂蒍�A���Ȃ̂��낤�B�����Ē����Ƃ͋N�����قȂ邱�Ƃ͂����܂Œ��X�_���Ă����Ƃ���ł���B
4.�o�_���̂x��`�q�n�v���^�C�v
���̑O�ɁA�o�_�����퐶�l�Ȃ̂��ꕶ�l�Ȃ̂��͔��f�̎d���������Ǝv���Ă���B
�o�_�l�̂x��`�q�n�v���^�C�v��D1a2�ł���A�p�̓V�c�A�I�z�h���͏o�_���o�g������D1a2�ŁA����͍����V�c�܂Ōq�����Ă���悤���B�����琴�a�����̎q���̋`�o�������炵���B
�����Č�����{�l��4�����炢��D1a2�Ȃ̂ŁA�ꕶ�l�͂��̂܂ܐ����c���Ă����Ȃ�ĝ�������邪�A����ƃA�C�k�̐l�����͂����ƍ��p�x�ƂȂ�̂́A���{�̒��S�����痣��Ă���A�c�������A�ǂ�ꂽ���Ȃ̂ŁA����͎��R���B
����������ƃA�C�k�̐l�����͕����I�ɏo�_���Ƃ̂Ȃ���͌��������Ȃ��ʏW�c�ł���B�P����D1a2�͓ꕶ�l�Ƃ͂����Ȃ��Ȃ�B
�o�_���́A�����l�ފw�I�ɂ͖퐶�l������ȍ~�̓n���l�Ɠ������x�������炾�B
���̌��ɂ��ẮA�ʂɍl�@���邱�Ƃ�\�肵�Ă���B
5.�T�C�m�J�~�M�����o�_����������_��
�O�֎R�̑�_�_�Ђƞw���_�Ђɂ́A�L���ȎO�c����������A�܂����A�����݂���B����_�Ђɂ����A���͂���B������ʓI�Ȓ���������B
�O�c�����ɂ́A�T�C�m�J�~�O�_�A�N�i�g�_�A�T�C�q���A�T���^�F�_���J���Ă���B
����܂ł̍l�@�ɂ��A���̎O�c�����͂�͂蒹���Ȃ̂ŁA�㐢�̂��̂Ȃ̂��낤���B
�O�֎R�����_�̂Ƃ����̂́A�o�_���ȑO�̏W�c�ł���ꕶ�l�⋌�Ί�l���s���Ă������J�̖��c�ł͂Ȃ����Ǝv���B�����͐_�Ђ̔q�a�ł͂Ȃ��A�֍��ō��J���s���Ă����ł��낤�B
������T�C�m�J�~�M�Ɋւ��ẮA���݂̓��c�_�̌��^���c����Ă���ƍl������B
���ē��c�_�̋N���ɂ��ẮA�o�_���̐_�ɋ��߂�E�����͂Ȃ��悤�ŁA���R��
��ɁA�Â����Ă��Ƃ��Ƃ̍Ր_���s��
��ɁA�L�I�ɂ��A�}�e���X�̌n�����グ���A���̒��ŏo�_���̐_������A���݂̉��ł���R�g�V���k�V�A�I�I�N�j�k�V���_�b�̒��ɕ����߂��A�n�_�n�̐_�ɂ��ꂽ���߁A���Ƃ��Ƃ̐M�ł���T�C�m�J�~�M�͔p�ꂽ�B�������z�_�M�͓s���ǂ��A�}�e���X�Ƃ����ˋ�̐_�Ɍ`��ς����B
�O�ɁA����l���A�_�ЂƂ����đz�N����_��(�����A�q�a�A�_�a)�Ƃ͎�قȂ�B

 �B��s����(141��������)���㓹�c�_�A�H�t������J���Ă���B���̑��ې���K�l�̐����ɕ��ׂ��Ă���B�T�^�I�ȊېΓ��c�_�B
�B��s����(141��������)���㓹�c�_�A�H�t������J���Ă���B���̑��ې���K�l�̐����ɕ��ׂ��Ă���B�T�^�I�ȊېΓ��c�_�B
6.���c�_�ɂ���
���c�_�ɂ��Ă�Wiki�́m���c�_�n�o�T:�t���[�S�Ȏ��T�w�E�B�L�y�f�B�A�iWikipedia�j�x������p���邪�A�m���c�n�Ƃ͒����̊T�O�ł���A�������ꂽ���̂��B
�u�S���I�ɍL�����z�����Ă��邪�A�o�_�_�b�̌̋��ł��铇�����ɂ͏��Ȃ��B�b�M�z�n����֓��n���ɑ����A�v
�u�_���Ƃ��Ă̏����j����10���I���ɕҎ[���ꂽ�w�a�����ڏ��x�ŁA11���I�ɕҎ[���ꂽ�w�{���@�،��L�x�ɂ́u�I�ɍ����ޔ{���c�_�v�i�P�͕s�ځj�̐��b���L����Ă���A�w���̕���W�x�ɂ��������e�̐��b���L����A�u�T�C�m�J�~�v�Ɠǂ܂��Ă���B��������́w�a�����x�ɂ��u���c�v�Ƃ������t���o�Ă��Ă���A�����ł́u���ւ̂��݁i�ǂ̐_�j�v�Ƃ����������Ă��A�O������̐N���҂�h���_�ł���ƍl�����Ă���[1]�B�v
�@
�Ƃ��邩���͂茳�̓T�C�m�J�~�M�ł��邱�Ƃ͊ԈႢ���Ȃ��B
���ɁA
�u���c�_�������������悤�ɂȂ����̂�18���I����19���I�ŁA�V�c�J���␅�H�����������ɍs���Ă��������ł���[5]�v
�Ƃ�����A�������g����n�ł́A��L�̂��Ƃ����Ă͂܂�\���͑傫���A�Ƃ���Ώo�_���̑��ՂƂ��āA���c�_������Ƃ͌����Â炢�_������B
�u���c�_�͗l�X�Ȗ������������_�ł���A���܂����`�͂Ȃ��B�ގ��͐ō��ꂽ���̂��������A�ō��ꂽ���̂ł����Ă����R����H���ꂽ���́A�ʐȂnj`��͗l�X�ł���[5]�B���̎�ނ��A�j�_�Ə��_�̏j������A����E���i�E�ڕ��Ȃǂ��`�ʂ��ꂽ���Ȃǂ̑o�̑��A���C�̑��A�j���A������Ȃnj��I�Ńo���G�e�B�ɕx��[5]�B
�P�̓��c�_
�P�̓�_���c�_
���c�_
�����^���c�_
�j���^���c�_[1]
���R���c�_
��ړ��c�_
�o�̓��c�_
�݂����c�_
�ېΓ��c�_
���d�����c�_�@�v
���Ɍ`�̂͗l�X�ł���A���^�����������̂����������������B
�o�̓��c�_�Ƃ͒j���������ŁA�j���̌������Ӗ�����悤�ɂƂ�A�݂����c�_�͉P�Ƌn�ŁA�q���h�D�[���̃����K(�j����)�ƃ��j(������)���A�j���`�͑��̐_�Ђł����_�̂ƂȂ邪�����K�ɑ������āA���B�퐒�q�ƍl������B
����āA�����̂��Ƃ̊T�O�͏o�_���̃T�C�m�J�~�M�Ɋ܂܂�Ă����Ǝ@�����A�q���h�D�[���̌��^�̓C���_�X�����ɋ��߂���̂ŁA��͂�ނ�̑c��̓h�����B�_�l�Ȃ̂����m��Ȃ��B
�u���c�_�͓��{�e�n�Ɏc����Ă���A�Ȃ��ł����쌧��Q�n���ő��������A���ɒ��쌧�̈��ܖ�͓��c�_�������y�n�ł悭�m���Ă���[5] [12]�B
���쌧���ܖ�s�ɂ͖�400�̂̐Α����c�_������A�s�����P�ʂł̐������{��ł���B���������쌧���{�s�ł����_�����ɖ�370�̂̐Α����c�_�����邪�v
���ɁA��A���v�X�s�̋���ψ���̒����y�A��
���A��A���v�X���ʔ����z 2021�N2��15�� (��)
https://sannichi.lekumo.biz/minamialps/2021/02/post-74b3.html�A�ł́A������A���v�X�s���ɂ�195���Ƃ����A�n�}�Ɏ����Ă���̂����A�����Ƃ��Ă͂����Ƃ���悤�Ɏv���B
�܂������ɂ́A�h�H�t����g�ƌĂ�鏬�����K�̂��̂�����A�����͏H�t�_�Ђƒ���ꂽ���_�̂̐�����B����͌㐢�ɕ������̂ł͂Ȃ����ƍl����B
�����́u�\�_�v�ƒ���ꂽ�����ׂ��邱�Ƃ�����B
���n�ɂ�����A���_�̂̍ނƂȂ�ɂ��Ăł��邪�A������̏㗬�̍b���x��P���O�R�Ȃǂ̎R�͉ԛ���Ő��藧���A�����̉͌��ɂ͑召�̉ԛ���̐��낪��������A�`��͊p������ۂ��`��̂��̂���������B���B�͗e�Ղł���B


���A���Ƃ��_�̂�����Ă����A�㐢�ړ��������̂��H��A���v�X�s�݉ƒˁ@���_�͍̂�����A�T�C�m�J�~�A�\�e��_�A�H�t����A���̑�
7.�T�C�m�J�~���Ղ�_��
�悸�N�i�g�_�́A�L�I�ɖ�����Ă͂��邪�A�I�I���}�c�~���i��R�_�_�j�Ɩ���ς��āA�O����ЁA��R�L�_�ЁA��R���v���_�ЂɍՂ��Ă���B
�N�i�g�́A��A�����́A�D�ˁA�Ԍ˂Ɩ���ς��A���݂͐������Ȃ����A�D�ː_�Ђ�Ԍː_�ЂɍՂ��Ă���B�����������_�Ђ̒����́A���A���ł͂Ȃ��B
���Ƃ��āA��錧�_���s�̑����_�Ёi����������j�̍Ր_�͋v�ߌː_�ł���A���Ђ͍���_�{�E�����_�{�ƕ���Łu�����O�Ёv�Ə̂����B
����_�{�E�����_�{�̍Ր_�͕��P�Ɛ_�i���䗋�_�A�^�P�~�J�d�`�j��
�o�Î��_�i�t�c�k�V)�ŁA���̋L�I�̐_�ł���B�܂����̓�Ђ͉ڈΕ���(������������)�̂��߂Ɍ��Ă�ꂽ�A����n�̈Ӗ������������A���}�g�^�P���̓����̃��[�g�ɂ���Ƃ����킯�ŁA���҂Ƃ������̒��쑤�A�������Ɖ����[�����Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B
�����A�����_�Ђ̓����̍Ր_�͏��쎨�̎q�A�_���䎨�ł���A�_���䎨�̎q���̕��ؔn�^�P�J�V�}���n�������Ƃ������ƂŁA���͏o�_���̐_�Ђ������������B�i�����́A�헤�̑厁���J���������̑�_�ŁA�O�֎R�̐_�Ɍq����Ƃ��������������A��ɒ��b�ɍ��J����D��ꂽ�j
�����_�Ђ̍Ր_�̓N�i�g�_�ł���A�Г`�ł́A��15�㉞�_�V�c�̑�ɑn���Ƃ��邩��L�I�ȑO�Ŏj���Ƃ���A���Ȃ�Â��A������������炻���͌o�Ă��Ȃ��B�o�_���̐_�ł��邩��A�L�F�R��ǂ��������߂ɖ쌩�h��R���֓�����ɔh������A��֓��Ɉڂ�Z�o�_�������Ă����A�����͂���ȑO�ɑ�F�ꑰ�����Ă��Ɛ������Ă��ǂ��C������B
�����ЂƂA���s�s�㋞�掛���ʍ��o���鐼��
�K�_���̍K�_�Ёi�����̂��݂̂₵��j�ŁA�Ր_�͉��c�F�ɂȂ��Ă��邪�A����������T�C�m�J�~�M�̐_�Ђł��邱�Ƃ�������B
�܂��A�u�K�_�Ёi�����̂��݂̂₵��ΐ_����j�vhttps://kyoto-k.sakura.ne.jp/jinjya1083.html�ɂ���.�u���̕ӂ�ɋ������܂��Ă����o�_���̎��_�ł������Ƃ������Ă��܂��B�v�Ƃ���B����͐��ɁA�R��Ɉڂ�Z���ΉƂ̌��ÔT�g�̖��Ⴊ���Ă��̂ł��낤�B
���ڂ����̂́A�N�i�g�_�A�K�m�_�A�T���^�F�������c�F�݂̂Ɋ������Ă��邱�Ƃł���A���̓��c�_�����l�ł���X���������悤�Ɋ�����B
���̓_�A����I�]�M�Ð_�Ђ̌����`���ɂ���悤�ɁA��F�̓T���^�_�̂��J��Ηǂ��Ɣ��f�����̂����m��Ȃ��B�㐢�̓��c�_�̓T�C�m�J�~�M�Ƃ͂܂��ʂ̕������������悤�ɂȂ����̂��낤��
���̉��c�F�̌��Ɋւ��Ă�
�u�c�_�͓�������R�������M�\�M�ƏK�����Đʋ������u����A���̂������]���Đ_���̉��c�F�_�Ƃ��K�������BWiki�́m��̐_�n�o�T:�t���[�S�Ȏ��T�w�E�B�L�y�f�B�A�iWikipedia�j�x�Ƃ�����A�����ł��Ȃ��B�����͌ォ��̂������Ȃ̂��͕s�����B
�܂��k��B�s��������K�_�꒚�ڂ́u�����̂��ݗl�v�K�_�_�Ђɂ́A���c�_�Ɖ��c�F���ʂɓ����ɕ���Ă��邻�����B�u�����̂��ݗl -�k��B�s.htm�vhttps://www.city.kitakyushu.lg.jp/yahatanishi/file_0048.html
���̐_�Ђ̏Z�����A�K�_�T�C�m�J�~�ł���B
�T�C�m�J�~�O�_�́A���Ƃ��Ƃ͂�͂�ʁX�Ɉ����Ă����̂����m��Ȃ��B
�W���𗝉����₷���悤�ɐ}������Ă݂��B
���c�_�́A�W���̓�����⓹�����ɔz����A�C�∫�������̂�����Ȃ��悤�ɂ��铭���́A�ǃm�_�Ƃ��B�ǂ����̊�������̂������Ă���悤�ɓ����̂́A�K�m�_�ƍl����ƕ�����₷���B
���c�_�̌ꌹ�ł��钆���́u���c�v���A����(����Ƃ������Ă���)�ǂ�Ȃ��ƂŏK���������ɂ��Ă͒��ׂ��t���Ă��Ȃ����A�T�C�m�J�~�M���ϑJ���Ă����ߒ��ł͑傫�Ȍ��ƂȂ�B
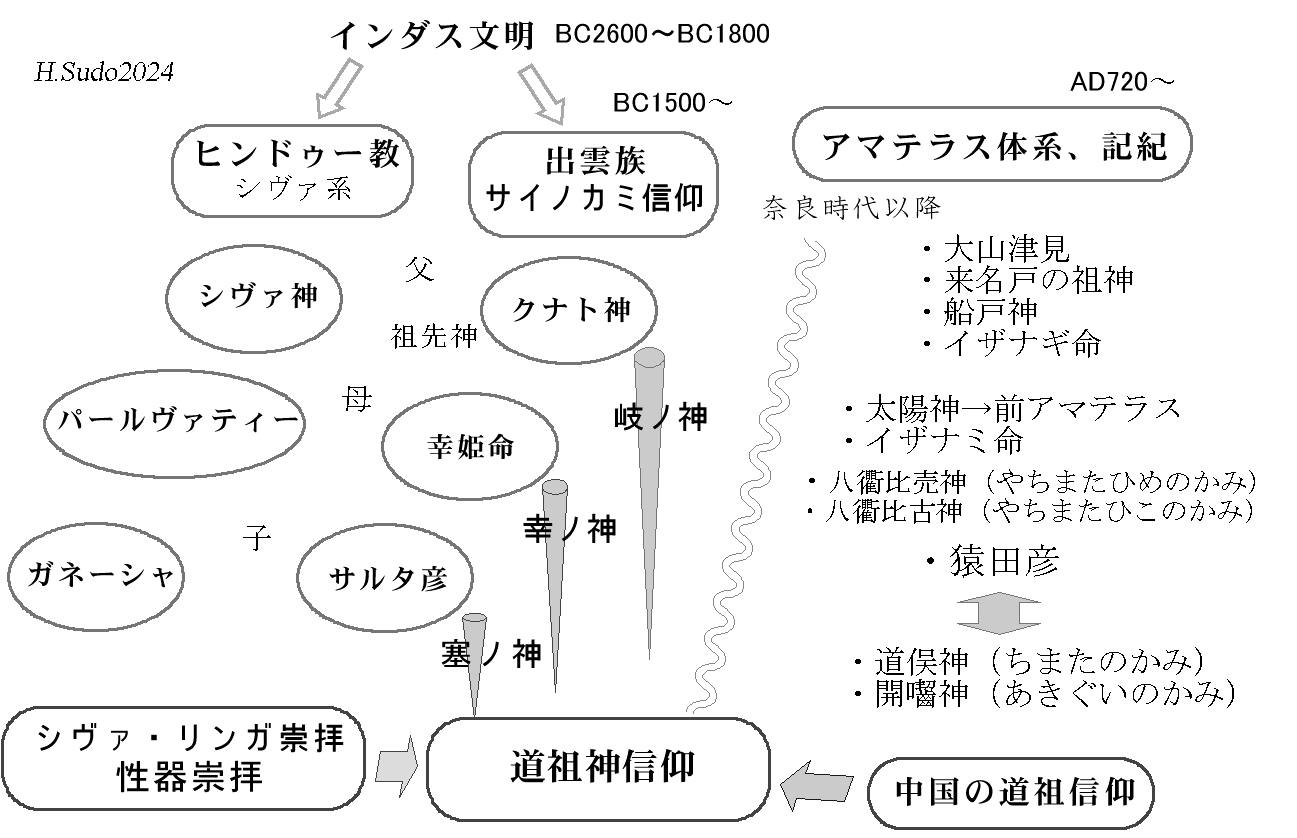
8.��F���͂Ɠ��c�_
���c�_�������c���Ă���̂́A�b�M�z�Ɗ֓��n���ɁA���k�Ⓦ�C�������ėǂ��Ǝv�����A��F��q�̕����͕ʂ̐��͂��y�n��Ƃ����������ł��������B
�N�i�g�_�M�ł͂Ȃ��A�T�C�m�J�~�M��A���n�o�L�M���g������������F�̈ӌ����w�i�ɂ��肻�����B
�܂���q�������A�o�̓��c�_�́A�V���@�E�����K���q�Ɍ�������悤�ɍl����B
�T���^�q�R�ƃA���m�E�Y����v�w�ɂ���̂͌㐢�̂������ł͂Ȃ����낤���A���Ȃ݂ɃA���m�E�Y���̌��^�́A�A���m�F�����ł���A�_�Ђɂ����܂��A��ɈÎE���ꂽ�L�P�ł���Ƃ����B
��������ƁA�N�i�g���ƍK�P�ł͂Ȃ����ƂɂȂ�B�ǂ��炪�����f���Ȃ̂��͕�����Ȃ����A�O�҂̏ꍇ�B�L�I�̐_�b�ɍ��������߂Ă��邱�Ƃ͊m���ł���B

 ���ʐ^�A�����䂪�X�̑o�̓��c�_�B���k�ɓ���Ƒo�̓��c�_���悭����悤�ɂȂ�B�E�ʐ^�A��{�̓S�p�C�v�ɂ�钍�A���A�����̃����K�̂悤�Ȃ��_�̂Ǝv��������ׂ��Ă���B���Ă����邱�Ƃ��猳�͏H�t���B
���ʐ^�A�����䂪�X�̑o�̓��c�_�B���k�ɓ���Ƒo�̓��c�_���悭����悤�ɂȂ�B�E�ʐ^�A��{�̓S�p�C�v�ɂ�钍�A���A�����̃����K�̂悤�Ȃ��_�̂Ǝv��������ׂ��Ă���B���Ă����邱�Ƃ��猳�͏H�t���B
9.�������̍Վ��ƃC���h�̃|���K���̋��ʓ_�Ɠ��c�_�A���A��
�@�b�B�ɂ́A�������ɍs����b�{���c�_�Ղ����邱�Ƃ͊��ɏq�ׂ����A��C���h�ɂ͂���ɂ悭�����APongal�i�|���K���j�Ƃ���1��15���ɍs����A�q���h�D�[���ȑO�̌Â��Ղ����邻�����B��C���h�̓h���r�B�_�l�����ݏZ��ł���y�n�ł���B
���ʓ_�́A���A��i���߂Ȃ�j��Ƃ̓����ɒ���B�Ƃ̖�ɃT�g�E�L�r�𗧂Ă�B���{�ł͖叼�ɑ������邩�B
����ł͏������̍Վ��Ɂu�䒌�v�Ƃ��������t����1�{�̍������ɏ����t����B�R���ł́u�䒌�v�Ƃ͌���Ȃ����A���l�̂��̂ł���B�������u�䒌�v�Ƃ����Ă��z�K��Ђ́u�䒌�Ձv�́u�䒌�I���o�V���v�Ƃ͊W�͂Ȃ��B
��(������|���K���Ƃ�����)������_�ɕ����āA�H�ׂ�B����͓��{�ł͎������ɑ������邩�B
�@�������ɐH�ׂ鏬�����Ɋւ��ẮA�u�Z������̒����암�ł�1��15���ɓ������H����ꂽ�i�w�t�^�Ύ��L�x�j�B���ꂪ���{�ɓ`�����1��15�����Ȃ킿�������̒��ɏ�������H����悤�ɂȂ����ƍl�����Ă���B�v�Ƃ�����B�w�t�^�Ύ��L�x�͓쒩���̏@��i�������j�ɂ���āA��������̌t�^�n���i���]������j�̔N���s�����L�������ł���̂ŁA��k���ȑO��蒆���암�̈�얯�����s���Ă����Վ��ł���ƍl���Ă悢���낤�B���ꂪ�C���h�ւ��`����ꂽ�\��������B
�����́w�t�^�Ύ��L�x�ɍ��������߂��Ƃ��A�퐶�l�W�c�̓n���ɂ�莝�����܂ꂽ�\���͑傫���B
Wiki�́m�������n�m�t�^�Ύ��L�n�o�T:�t���[�S�Ȏ��T�w�E�B�L�y�f�B�A�iWikipedia�j�x���
���̑��ɂ́A�ǂ�ǏĂ��A�m�ō���������╨���Ă��Ȃǂ����邻�����B���̓��c�_�Ղ�ł͉Ղ�ƂȂ�B
���A���̋N���ƃh�����B�_�Əo�_���Ƃ̊֘A�ɂ��ẮA�����I�ł���B
���ɂ́A��͂�w�t�^�Ύ��L�x�ɂ��A�u�����\�ܓ��A����(�������������H)�����A���p�𑴂̏�ɉ����A�ȂĖ�˂��K��B���̗[�A���Ƃ��}���A�Ȃď����̎\�K��m���A�ďO����肤�v�Ƃ���BWiki�́m�������n�o�T:�t���[�S�Ȏ��T�w�E�B�L�y�f�B�A�iWikipedia�j�x���
�ĕ��ō�������ʂ̏��������ė\�j���s�����Ƃ��A���݂܂ő������Ă���B
���c�_�ɕ���ŁA�\�_���J���Ă��邱�ƂɌq�����Ă���̂��낤�B
�������̍Վ��Ƃ́A�_�k�������܍��L���▚�ʂ̖L�������čs�����ƂɗR�����Ă��邱�Ƃ�������B
�܂����c�_�ɂ͌㐢�A�Ε����̐_�ł���H�t����(�H�t�R)�����ׂčՂ��Ă��鎖�ɂ��Ă͊��ɏq�ׂ����A���݂݂��铹�c�_�̐��藧�������L�Ɏ����B
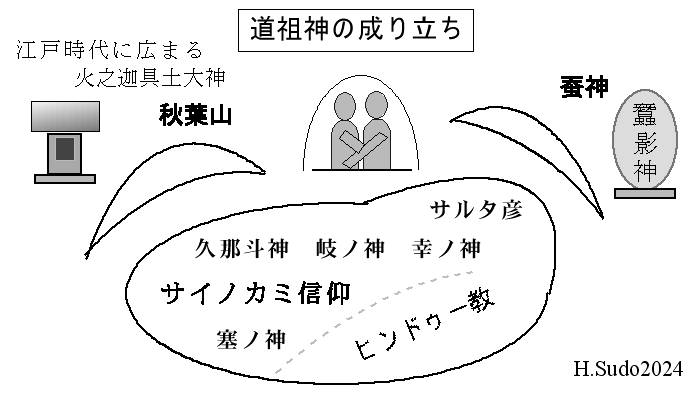
10.�������ƃT�C�m�J�~�Վ�
���c�_�Ƃ͗���āA�������ɃT�C�m�J�~�݂̂̍Վ����s���Ă������A�������̕�����Y�I�����C��https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/170885 https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/223539����̈��p����B
�Ղ�̓��e��v��ƁA�T�C�m�J�~�̐l�`�����A����������Ă���R�₷�Ղ�ł���B�T�C�m�J�~�̐l�`�ɁA��N�Ԃ��q�����w���킹�Ă���R�����P���Ƃ�����|�ɂƂ��B�o�_�����L�߂��T�C�m�J�~�M�́A�_�k�����I�ȐF������[�����āA���݂܂Ōp�����Ă���B
 ��A���v�X�s�L��䒺�g�����ف@�������̏���t���H1/16�B�e
��A���v�X�s�L��䒺�g�����ف@�������̏���t���H1/16�B�e
�E��ÎO���̃T�C�m�J�~
�u�O���̃T�C�m�J�~�́A�܍��L���△�a���ЁA��Ƃ��Ȃǂ��F�肵�čs���鏬�����̉Ղ�ł���B�����̋{���A�K���A��o�A���A�O���A��J�A�����A�ꌴ�̊e�n��ƁA�����n��̂P�R�����ōs����B
�@ �ᓥ�݂����č�������ɁA�R�����o�����_���^�сA����Ɋe�Ƃ���W�߂���������Ȃǂ����ė��āA��ɂȂ�ƔR�₷���̂ŁA���̍�蕨���T�C�m�J�~�ƌĂԁB�ᓥ�݂��������W�߂�͎̂q�ǂ������̎d���ŁA�_�̒�T�C�m�J�~�̓_�Ȃǂ͖�N�̒j�����s�����Ƃ������B
�@��Ƃ��̂� �߁A��N�̒j���ɂ��~�J���T���⑺�l����N�̒j����S���ŔR������T�C�m�J�~�̎��͂��܂��s�����s����B�܂��A�T�C�m�J�~�̔R�����ŖL�������� ��A���̉ɂ���������A�݂Ȃǂ��Ă��ĐH�ׂ�ƕa�C�����Ȃ��ȂǂƂ������B�v
�E�W���̃T�C�m�J�~�@�x�R�����V��S���P���@
�u�W���̃T�C�m�J�~�́A����△�a���ЁA�܍��L���Ȃǂ��F�肷�鏬�����̉Ղ�ł���B�������A�q�ǂ��������A�T�C
�m�J�~�̉S���̂��Ȃ���ƁX��K�₵�Đ���������W�߁A�َq�Ȃǂ����炤�B���̂Ƃ��ŔN���̎q�ǂ����f�N�Ƃ����j����̖ؐ��̐l�`�����B�q�ǂ�������
�e�Ƃ����ԁA�n��̋��ł͒|�Ƙm�ʼn~���`�̍�蕨�������B�q�ǂ����������I����ƁA�f�N�𐳌�����ƂƂ��ɍ�蕨�̒��ɔ[�߂ĉ�����B�f�N��
���S�ɊD�ɂȂ�܂ŔR�₵�čs���͏I������B�v
11.���݂Ɍ��钍�A���ƒ����̋��
�ߏ��ɂ��铹�c�_�ׂ����ɋ����[���`�����������B
����~�n�ɏH�t����ƃT�C�m�J�~���ʁX���J���Ă��鎖��ŁA�����ƒ��A�����A�㐢�������ɋ�ʂ���Ă��邱�Ƃł���B
��A���v�X�s�S�X�ɂ����ƁA�k�m�s���⒬��䃖�X�̗�ł���A���ʂ��邱�Ƃ́A�p�n���L���Ƃ����_���B
�܂��H�t������K�́A���Ƃ͈�˂ɂЂƂ���̂ł͂Ǝv���A���Ƃł͕~�n�����J���Ă���B����������������B


���ʐ^�A��A���v�X�s�S�X�̉��c�F���E��O�A�ƏH�t���̖؉��B�E�ʐ^�A�H�t����ɂ͒���������A�E���ɃT���^�q�R���B�㐢�����������͗l�B


���ʐ^�A���c�F���B�E�ʐ^�A�H�t����A�V���Ȓd���J���Ă��邪�A���Ă͖Y�ꂽ�̂��B

 ����A��䂪�X�B����~�n���A���ʐ^�A�����ƏH�t����A���[�̐Δ�ɂ͏H�t�_�Ђƍ��܂�Ă���B�E�ʐ^�A���A���A�T�C�m�J�~�_�A���_�͍̂��̃����K�B
����A��䂪�X�B����~�n���A���ʐ^�A�����ƏH�t����A���[�̐Δ�ɂ͏H�t�_�Ђƍ��܂�Ă���B�E�ʐ^�A���A���A�T�C�m�J�~�_�A���_�͍̂��̃����K�B

 ���������{�����̓��c�_�ł��T�C�m�J�~�ƏH�t����ʂ����J���Ă���B�R���ɂ��Ă͕����N�Ԃɔ����F�A�����P��_�Ƃ̐_�Ƃ����J�����炵���|�̋L�ڂ���B�Ր_�͔��˔䔄�_�E���˔�Ð_�Ƃ̂��ƁB�������A�����ɂ͒��A�����������Ȃ��B
���������{�����̓��c�_�ł��T�C�m�J�~�ƏH�t����ʂ����J���Ă���B�R���ɂ��Ă͕����N�Ԃɔ����F�A�����P��_�Ƃ̐_�Ƃ����J�����炵���|�̋L�ڂ���B�Ր_�͔��˔䔄�_�E���˔�Ð_�Ƃ̂��ƁB�������A�����ɂ͒��A�����������Ȃ��B

 �ߏ��������{�A�_�Ђɕ�����J���Ă����B���ʐ^�A�{�_�Ж{�a�ׂ̗ɂ��铹�c�_�A�E���ɓ��c�_��������B�E�ʐ^�A���A��������A�E�ɂ͏H�t����̓��Ă�����ł���B�K�͍����ɐ��܂Ƃ߂��Ă���B�T�C�m�J�~��3����A�����ې�2����B
�ߏ��������{�A�_�Ђɕ�����J���Ă����B���ʐ^�A�{�_�Ж{�a�ׂ̗ɂ��铹�c�_�A�E���ɓ��c�_��������B�E�ʐ^�A���A��������A�E�ɂ͏H�t����̓��Ă�����ł���B�K�͍����ɐ��܂Ƃ߂��Ă���B�T�C�m�J�~��3����A�����ې�2����B

 �B��s��������̏�A�T�C�m�J�~�A�E�͎\�_�B�H�t����͏������ꂽ�Ƃ�����J���Ă���B�܂��H�t����͓��Ă����Ƃ������B
�B��s��������̏�A�T�C�m�J�~�A�E�͎\�_�B�H�t����͏������ꂽ�Ƃ�����J���Ă���B�܂��H�t����͓��Ă����Ƃ������B
 ��A���v�X�s����(52��������)�A������T���^�F�H�A�T�C�m�J�~�A�H�t�_��
��A���v�X�s����(52��������)�A������T���^�F�H�A�T�C�m�J�~�A�H�t�_��
 ��A���v�X�s����V�������_(52����)�̓��c�_�A�������̍Ղ�̎��ɂ͒��S�I�ȓ��c�_�B���̐͏H�t�_�Ђƍ��܂�Ă���B
��A���v�X�s����V�������_(52����)�̓��c�_�A�������̍Ղ�̎��ɂ͒��S�I�ȓ��c�_�B���̐͏H�t�_�Ђƍ��܂�Ă���B
 �B��s����
�B��s����
 ���A���Ƃ��_�̂�����Ă����A�㐢�ړ��������̂��H��A���v�X�s�݉ƒˁ@���_�͍̂�����A�T�C�m�J�~�A�\�e��_�A�H�t����A���̑�
���A���Ƃ��_�̂�����Ă����A�㐢�ړ��������̂��H��A���v�X�s�݉ƒˁ@���_�͍̂�����A�T�C�m�J�~�A�\�e��_�A�H�t����A���̑�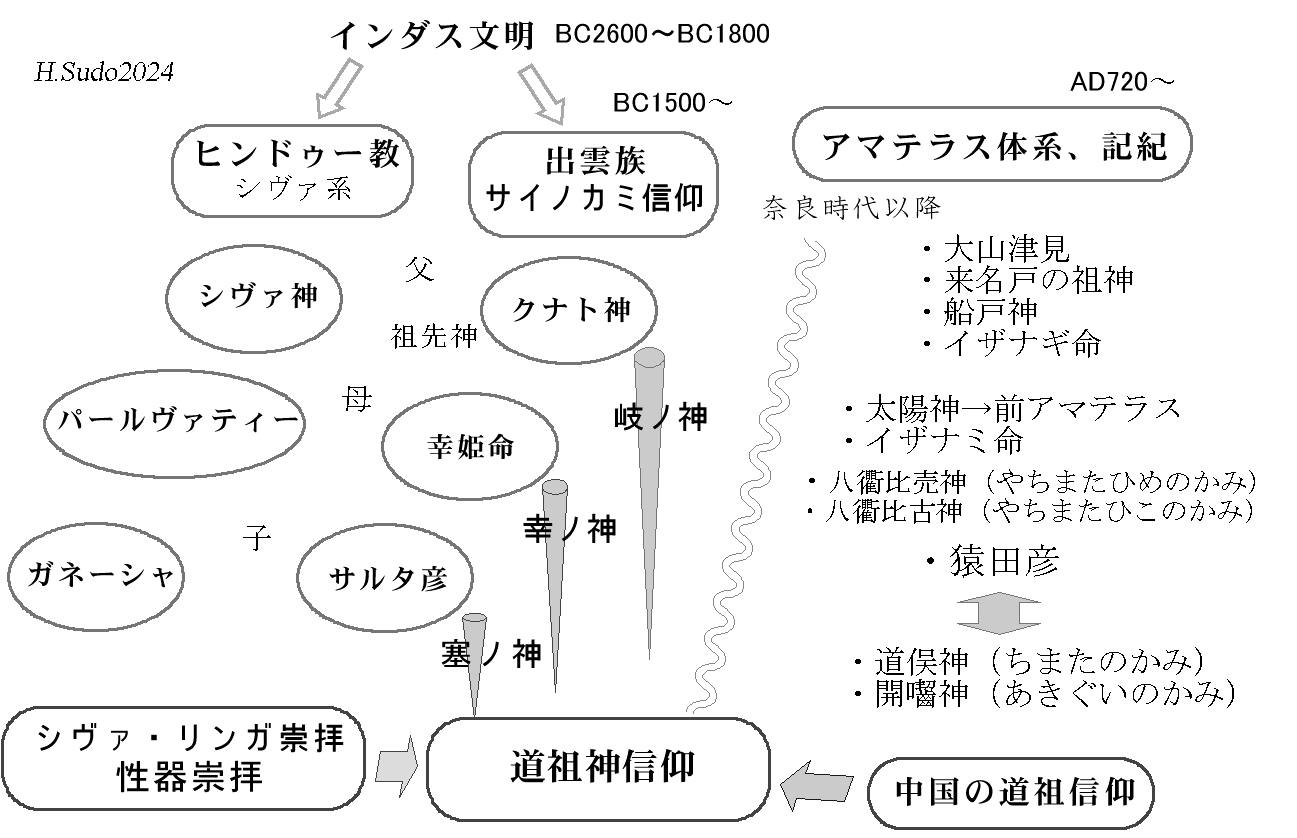

 ���ʐ^�A�����䂪�X�̑o�̓��c�_�B���k�ɓ���Ƒo�̓��c�_���悭����悤�ɂȂ�B�E�ʐ^�A��{�̓S�p�C�v�ɂ�钍�A���A�����̃����K�̂悤�Ȃ��_�̂Ǝv��������ׂ��Ă���B���Ă����邱�Ƃ��猳�͏H�t���B
���ʐ^�A�����䂪�X�̑o�̓��c�_�B���k�ɓ���Ƒo�̓��c�_���悭����悤�ɂȂ�B�E�ʐ^�A��{�̓S�p�C�v�ɂ�钍�A���A�����̃����K�̂悤�Ȃ��_�̂Ǝv��������ׂ��Ă���B���Ă����邱�Ƃ��猳�͏H�t���B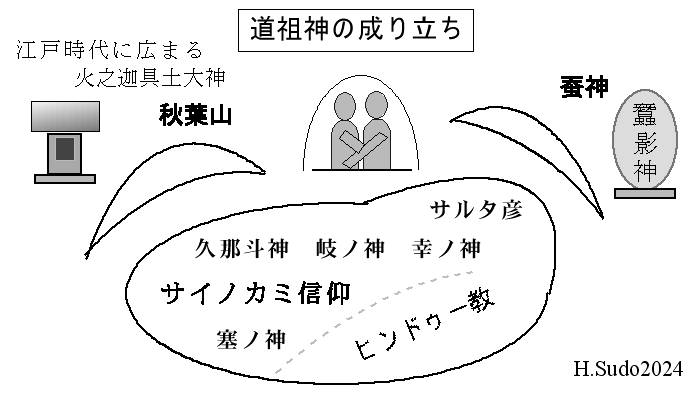






 ����A��䂪�X�B����~�n���A���ʐ^�A�����ƏH�t����A���[�̐Δ�ɂ͏H�t�_�Ђƍ��܂�Ă���B�E�ʐ^�A���A���A�T�C�m�J�~�_�A���_�͍̂��̃����K�B
����A��䂪�X�B����~�n���A���ʐ^�A�����ƏH�t����A���[�̐Δ�ɂ͏H�t�_�Ђƍ��܂�Ă���B�E�ʐ^�A���A���A�T�C�m�J�~�_�A���_�͍̂��̃����K�B
 ���������{�����̓��c�_�ł��T�C�m�J�~�ƏH�t����ʂ����J���Ă���B�R���ɂ��Ă͕����N�Ԃɔ����F�A�����P��_�Ƃ̐_�Ƃ����J�����炵���|�̋L�ڂ���B�Ր_�͔��˔䔄�_�E���˔�Ð_�Ƃ̂��ƁB�������A�����ɂ͒��A�����������Ȃ��B
���������{�����̓��c�_�ł��T�C�m�J�~�ƏH�t����ʂ����J���Ă���B�R���ɂ��Ă͕����N�Ԃɔ����F�A�����P��_�Ƃ̐_�Ƃ����J�����炵���|�̋L�ڂ���B�Ր_�͔��˔䔄�_�E���˔�Ð_�Ƃ̂��ƁB�������A�����ɂ͒��A�����������Ȃ��B
 �ߏ��������{�A�_�Ђɕ�����J���Ă����B���ʐ^�A�{�_�Ж{�a�ׂ̗ɂ��铹�c�_�A�E���ɓ��c�_��������B�E�ʐ^�A���A��������A�E�ɂ͏H�t����̓��Ă�����ł���B�K�͍����ɐ��܂Ƃ߂��Ă���B�T�C�m�J�~��3����A�����ې�2����B
�ߏ��������{�A�_�Ђɕ�����J���Ă����B���ʐ^�A�{�_�Ж{�a�ׂ̗ɂ��铹�c�_�A�E���ɓ��c�_��������B�E�ʐ^�A���A��������A�E�ɂ͏H�t����̓��Ă�����ł���B�K�͍����ɐ��܂Ƃ߂��Ă���B�T�C�m�J�~��3����A�����ې�2����B